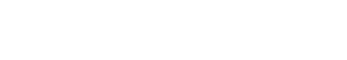星降りの松ほしくだ
徳川三代将軍(1623〜51年)家光公の頃のお話です。当時の住職の賢融(けんゆう)和尚が、虚空蔵菩薩のご真言を100万回唱える「虚空蔵求聞持法(こくうぞうぐもんじほう)」という修行を行いました。「虚空蔵求聞持法」は弘法大師空海も若い頃に高知の室戸岬で行い、修行最後の日に天から明星が舞い降りてきた「明星来影(みょうじょうらいえい)」という伝説が残されています。賢融和尚も何日も修行を続け、ついに終わるというその時、天から星が降ってきて境内のひときわ高い松の上で留まり、辺り一面を照らして輝きました。村人たちはこの不思議な光景を目の当たりにして驚き、熱心に星を拝みました。やがて星は落ちて石になりましたが、善養寺ではこの石を「星精舎利(せいせいしゃり)」と呼び、寺宝として今も大切にしています。善養寺の「星住山」という山号はこのお話に由来します。星が降った松は「星降りの松」として有名になりましたが、残念ながら昭和15年に枯れてしまい、現在は二代目が大きく育っています。


影向の石ようごう
昔、小岩あたりで盗人があちこちの家に押し入り、荒らしまわったことがありました。その盗人は善養寺の不動堂にも入って、大事な仏具を盗み出そうとしました。大きな風呂敷をかついで、境内の大きな松の下まで来たときのことです。片方の足が敷石にくっついて離れなくなってしまいました。「おや、困ったぞ、どうしたんだろう。ウーン、離れろ!」一生懸命に力を入れても、足はぴったりとくっついてびくともしません。「あーどうしよう、ぐずぐずしていると捕まってしまう。困った、困った」
すると突然、慌てている盗人の目の前に、右手に剣、左手に縄をもち、大きな目を見ひらいて怒りをあらわにした恐ろしい姿の仏さま「不動明王」が現れました。お不動さまは盗人の胸元に剣を突きつけこう告げました。「自分で働かないで、よその人のものを盗むなど悪いことばかりしている。この剣で突きさして命をちぢめてやるか。それとも、盗みなどはやめて、真面目にしっかり働くか。どちらにするか」さすがの盗人も「もうこれからは決して悪いことはいたしません。どうか命だけはお助けください」と涙を流して許しを願い、これまでの罪の深さをさとりました。そのとたんに、足が敷石からぱっと離れて、お不動さまの姿も見えなくなりました。影向の松の根元には、盗人のわらじの足跡が残っている「影向の石」があります。

むじな啓けい
善養寺の北側に木がたくさん茂っていて、昼でもうす暗い裏山になっていたころの話です。和尚さんが朝のお経をすませて裏山の方に回ってゆくと、一匹のむじなが死んでいるのを見つけました。和尚さんは「これはかわいそうなことじゃ。生あるものは、命を落としたあとも大切にあつかわなくてはいけない。ナムアミダブツ、ナムアミダブツ」と、ひとりごとを言いながら、墓地の中に穴を掘って、ねんごろにとむらってやりました。和尚さんが穴を掘っていると、地面の中から瓦のような板が出てきました。「おや、これは磬ではないか」磬はお経を唱える時に叩いて音を出す道具です。和尚さんはこの磬をつかって、朝夕本堂でお経をあげることにしました。
あるとき、お経が終わったあとに、ふと境内のほうを見ると、たくさんのむじなが集まっていて、本堂に向かって手を合わせるようなかっこうで仏さまを拝んでいました。それからしばらくたったある年のこと。近所に野火があって、火はどんどん燃え広がり、ついにお寺にも火が付きそうになりました。和尚さんは本堂で一生懸命に磬を叩きながら、火がおさまるようにお祈りしました。すると、どこからともなく大勢のむじなが出てきて、たちまち火を消しとめて、お寺が火事にならないように守ってくれたのです。それ以来、この磬を「むじな磬」と呼んで、お寺の宝物として大切にしています。

雨の植木市
かつて善養寺では毎年三月に植木市が開かれていました。江戸時代から続く年中行事で、残念ながら現在は行われていませんが、この植木市の日には必ず雨が降る、と言い伝えられていました。植木市が始まって間もない頃、境内の星降りの松の根元に、弁天さまの生まれ変わりといわれる白蛇が住んでいました。植木市のある日のこと、ひとりの植木屋さんが、弁天さまの生まれ変わりとも知らずに、白蛇を気味悪がって殺してしまいました。すると、今まで晴れていた空にたちまち黒い雲がわき上がってきて、大粒の雨がザーザーと降り出してきました。それ以来、植木市には必ず雨が降るので、「雨の植木市」と呼ばれるようになったそうです。
「昭和の俳聖」と呼ばれる石田波郷(1913~69年)は、昭和32年、読売新聞コラムに植木市の様子を記しています。「境内を埋めた植木の間を、縁日のような人出だ。ハンテン姿の日焼けした植木屋が埼玉弁で客を呼ぶ。安行から来たのだ。『神武以来売れない市だよ、昨日2000円のツバキが1本売れただけだ』この植木市にも伝説があって、江戸時代から続いているが、ある年植木屋が星降りの松に住んでいた白蛇を殺したところ、一天にわかにかきくもって、それ以来植木市には必ず雨が降るようになったという。「雨の植木市」である。『こういい天気だとヒヤカシばかり多くって木をいためられていけねぇ。雨なら木のためにもよし、買わねえ者は来ねえからナイ』植木屋から見た雨の功徳である。林立する植木の間に、ツバキ、モモ、ウメ、コブシの花が誇らかに花を見せ、大小の鉢、草花、球根に至るまで、植木の大祭典であり、4月1日から始まる緑の週間の前奏曲である。家に帰ったら、伝説にたがわず夕方から雨になった。」
不動堀のどじょう
当山第九世住職の賢融和尚のお話です。ある時、和尚をたずねて知り合いの禅宗のお坊さんがやってきました。二人はさっそく大好物の「どじょう鍋」をつつきながら、般若湯(お酒)を飲みはじめました。最初は気分よく話していましたが、酔いが回るにつれて口げんかとなり、しまいには禅宗のお坊さんが叫びました。「お前はさっきからえらそうなことばかり言っているが、それならこの鍋の中のドジョウを生き返らせられるか!」すると和尚は「できるとも」と言って鍋の中のどじょうを箸でつまみ上げ、お経を唱えました。そのどじょうを目の前のお堀へと放り込むと、なんとどじょうはスルスルと泳ぎだして、どこかへ行ってしまったということです。
袖かけの松
徳川三代将軍家光公の頃のお話です。ある時、ひとりの漁師が江戸川に舟を浮かべて夜釣りに出かけました。どうしたことか、その日にかぎって魚は一匹も釣れません。夜もふけてきたので、あきらめて帰ろうと思ったとき、針に何か重たいものがかかりました。「やっと釣れたぞ」急いで竿を引き上げてみると、それは17、8歳くらいの若い娘の水死体でした。漁師はかわいそうに思って近くの善養寺まで運び、ねんごろに葬ってもらいました。このことがあってから、境内の池のそばの松の根元に、何かを思いつめたように、しょんぼりと立ったまま首をうなだれている娘の幽霊が出ると、村中に噂が広まりました。そこで善養寺の和尚さんは、これはきっと何か心のこりがあるので、成仏できないでいるに違いないと思い、その娘のお墓の前に行って語りかけました。「娘さん、悩みごとがあるなら何でも言ってごらん。この和尚にできることなら、きっとかなえてあげよう」次の晩、和尚さんが池のほとりに行くと娘の幽霊が現れて「私の家は貧しくて、せっかく決まった縁談も、嫁入りの支度ができないので無くなってしまいました。もうこれ以上生きていても幸せになれないと思い、江戸川に身を投げたのです」と美しい顔をくもらせて、さめざめと泣きました。和尚さんは若い年ごろで死んだ娘をふびんに思い、さっそく江戸に行ってひとそろいの晴れ着を買ってきて、幽霊の出る松の枝に掛けておきました。翌朝、和尚さんが松のところに行ってみると、晴れ着がなくなって、代わりに白い小袖がひらひらと枝に揺れていました。その日から娘の幽霊は出なくなったということです。善養寺の池は今では埋め立てられ、袖かけの松もすでに枯れてしまい残っていません。